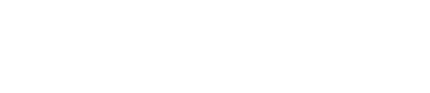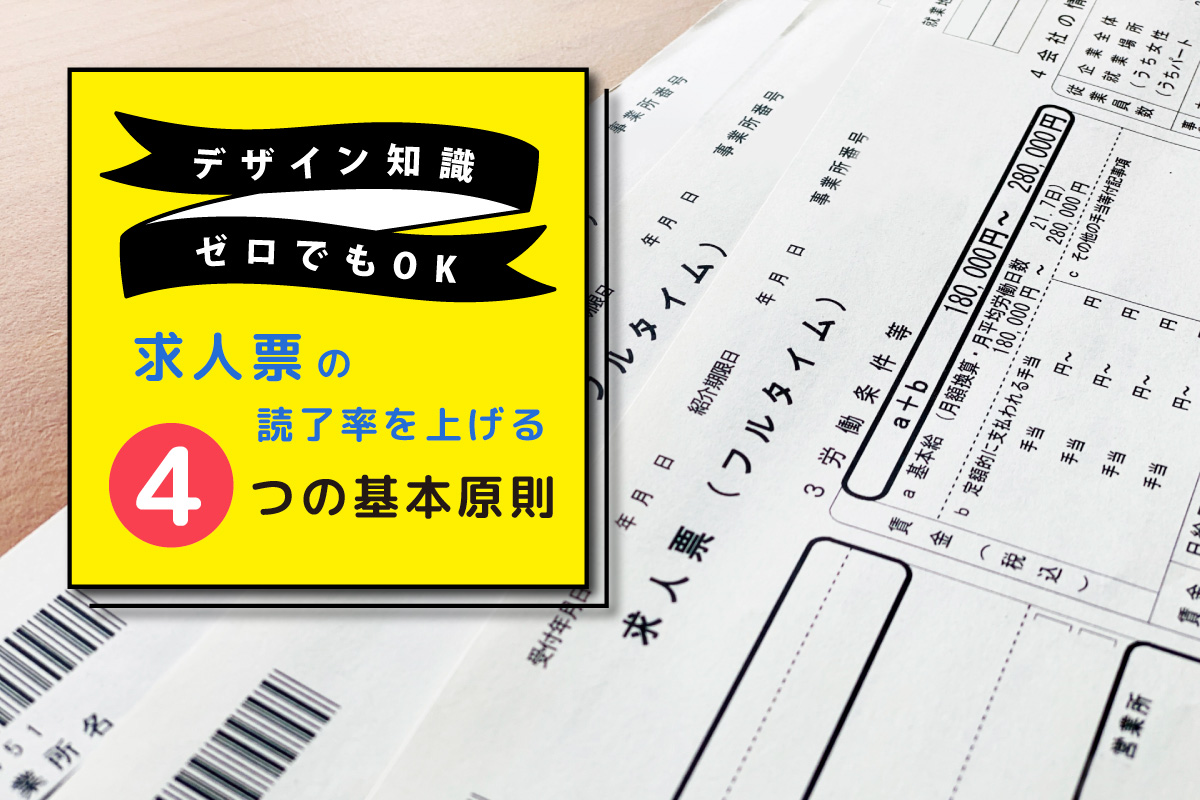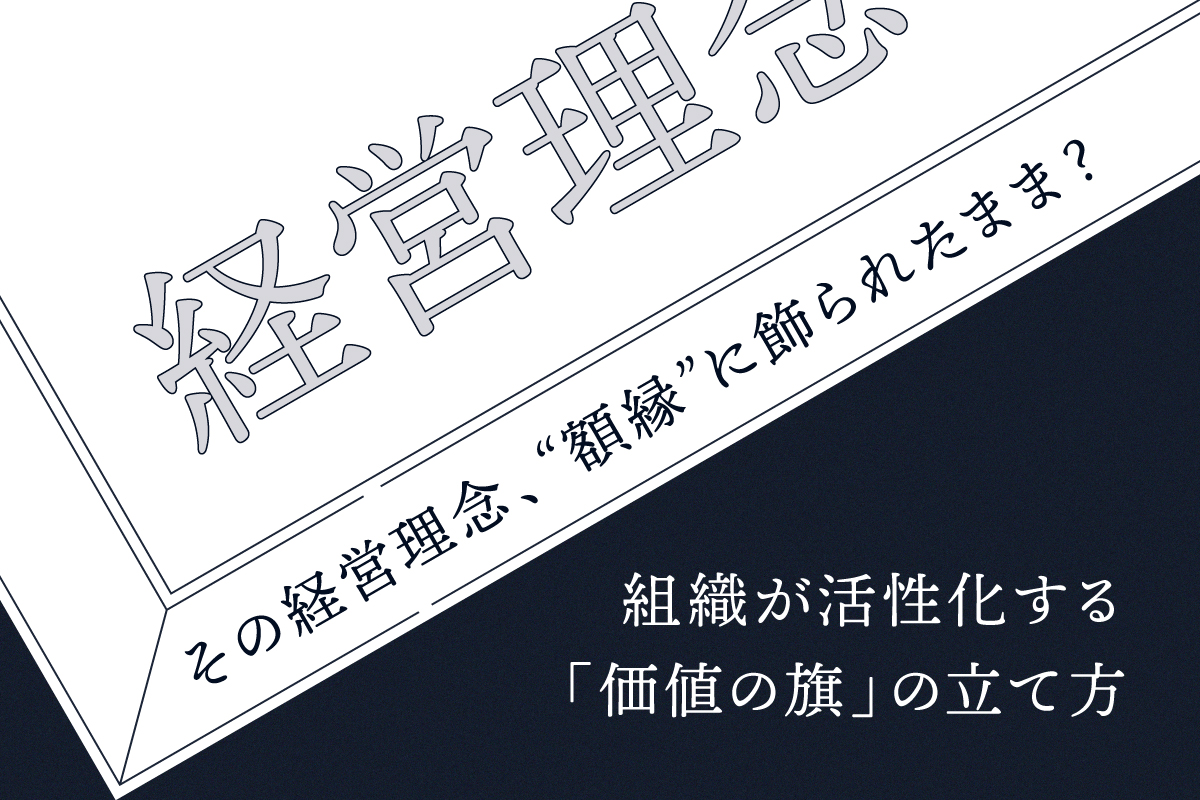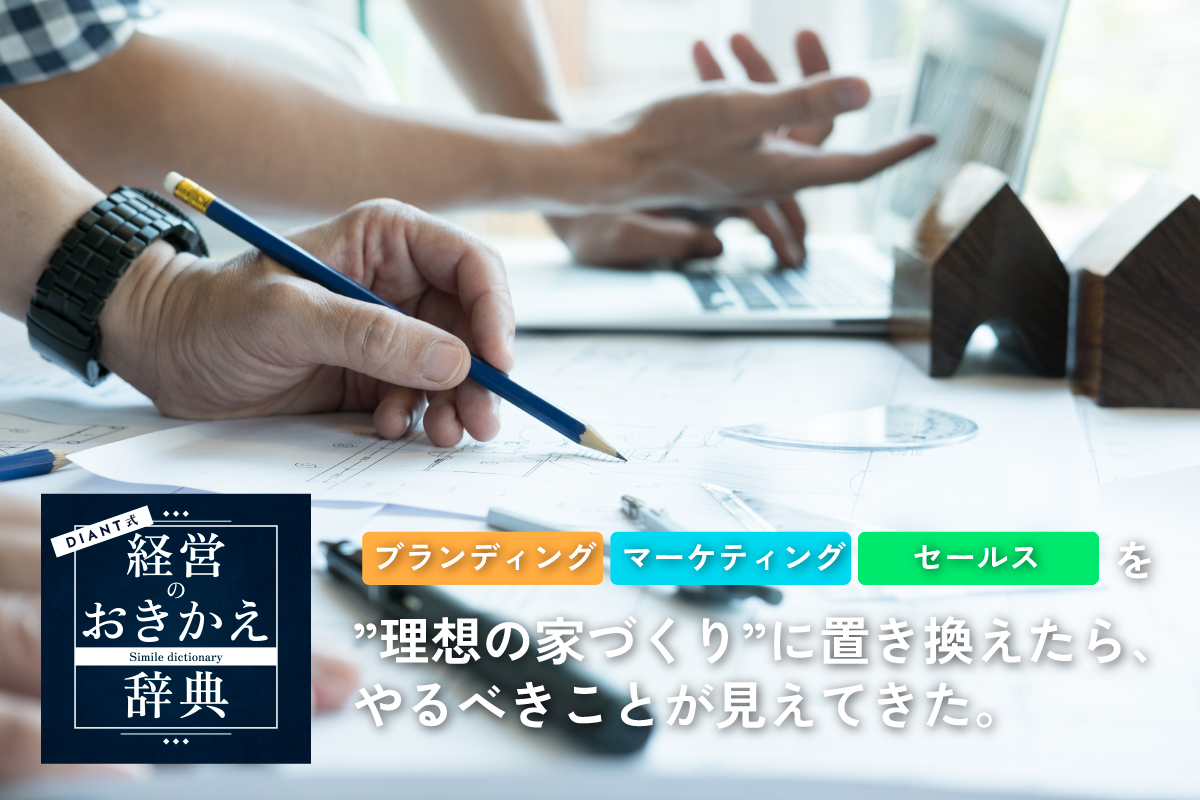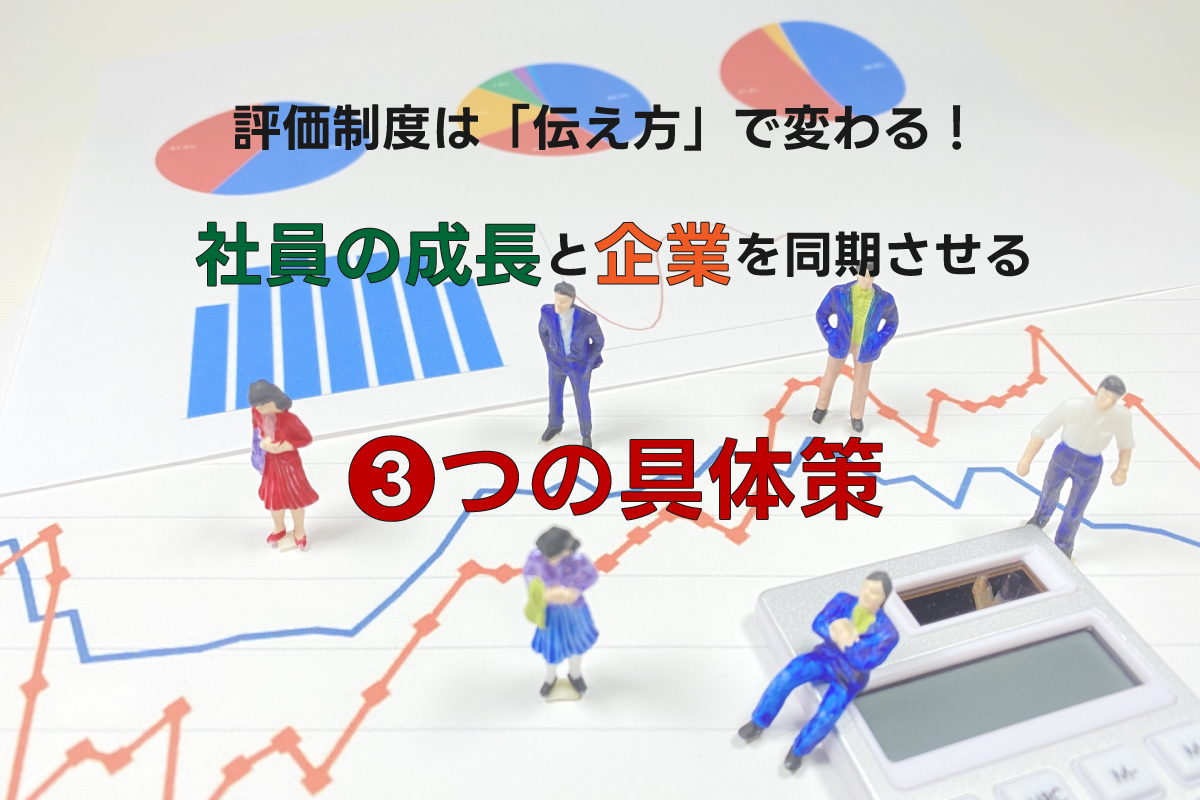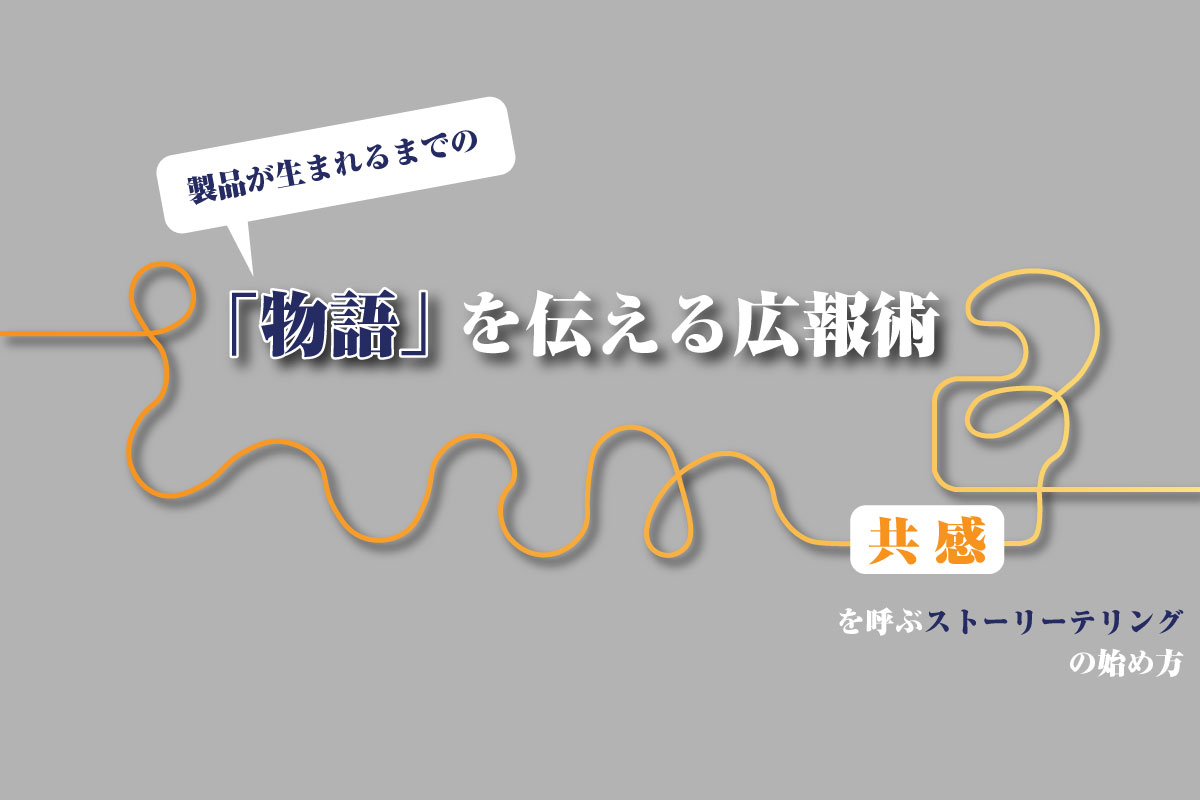この記事の目次
「らしさ」を見失っていませんか? 社員と共に、会社の未来を照らす「お宝」を発掘しよう

「長年会社を経営してきたけれど、改めて『ウチの本当の強みって何だろう?』と、ふと立ち止まってしまう…」
「お客様は本当に満足してくれているのだろうか? もっとやれることがあるんじゃないか…」
創業社長として会社を牽引してこられた経営者の方なら、一度はこんな想いを抱いたことがあるのではないでしょうか。
市場が目まぐるしく変化し、競争が激化する中で、知らず知らずのうちに自社ならではの「らしさ」や「本当に提供できる価値」が見えにくくなり、成長が鈍化したり、採用に苦戦したり…そんな漠然とした不安を抱えていらっしゃるかもしれません。
しかし、その不安を解消するヒント、そして会社の未来を明るく照らす“お宝”は、実は遠くにあるのではなく、会社の中に、そして日々業務を支え、お客様と真摯に向き合っている社員一人ひとりの中にこそ眠っているものです。
社長一人の視点だけでなく、多様な経験や立場を持つ社員を巻き込んで、「私たちの会社が、お客様や社会から本当に必要とされ、愛される理由は何なのか?」=「お宝」を共に掘り起こすこと。
それは、単に「強み」をリストアップする作業ではありません。
社員一人ひとりが自社の価値を再認識し、納得感を持って未来のビジョンを共有することで、社員の主体性を引き出し、組織の一体感を高め、そして何よりも顧客や社会から深く「共感」される、本物のブランドを築き上げる絶好の機会となるのです。
本記事では、そのような「共感型ブランドの源泉」を社員の皆様と共に発見するための、具体的な「ワークショップ実践マニュアル」をお届けします。このワークショップを通じて、貴社ならではの“お宝”を発見し、社員一丸となって自信を持って未来へ踏み出すための一歩としましょう。
ワークショップ準備編:実りある「お宝発掘」のための段取りと心構え

効果的なワークショップは、周到な準備から始まります。社員の皆さんが安心して本音を語り合い、創造的なアイデアが生まれる場にするために、いくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。
参加者選定のポイント:「多様な視点」こそが新たな発見を生む
「誰に参加してもらうか」は、ワークショップの成果を左右する非常に重要な要素です。
偏った意見ではなく、多様な視点が集まることで、思いもよらない「お宝」が発見されることがあります。
- 部署の多様性: 営業、開発・技術、製造、カスタマーサポート、管理部門など、できるだけ多くの部署から代表者を選びましょう。それぞれの立場から見える「会社の顔」は異なります。
- 経験年数の多様性: 長年会社を支えてきたベテラン社員の知見と、新しい視点を持つ若手・中堅社員の意見を組み合わせることで、議論に深みと広がりが生まれます。
- 役職の多様性: 経営層だけでなく、現場の最前線で活躍する社員の声も積極的に取り入れましょう。
- 最適な人数: 活発な議論と全員参加を促すためには、5名~15名程度が理想的です。多すぎると意見が出しにくくなり、少なすぎると視点が偏る可能性があります。グループ分けをする場合は、もう少し多くても対応可能です。
- 事前に伝えること: 参加者には、ワークショップの目的(例:私たちの会社の“お宝”をみんなで見つけ、未来の力にすること)、期待する役割(例:役職や立場は一旦忘れ、一人の会社の仲間として自由に意見を出してほしいこと)、大まかな進め方などを事前に共有し、安心して参加できる雰囲気を作りましょう。
事前課題でウォーミングアップ:各自の「想い」を持ち寄る
ワークショップ当日、いきなり「強みは何ですか?」と聞かれても、すぐに言葉が出てこないかもしれません。
事前に各自で考えを深めておくことで、当日の議論がより活発になり、多様な意見が出やすくなります。
事前課題のアイデア例
- 「私が思う、うちの会社の『一番の強み』と『もっと良くなるところ』」
- 「これまでお客様から最も感謝された、忘れられないエピソード」
- 「この仕事をしていて、一番『やっててよかった!』と感じる瞬間」
- 「もし、うちの会社が『最高の会社』になるとしたら、どんな会社になっていると思う?」
- 「他社にはない、うちの会社ならではの『こだわり』や『大切にしていること』は何だろう?」
事前課題の目的
これらの問いについて事前に考えてもらうことで、参加者は自分自身の経験や想いを整理し、ワークショップ当日に「自分の言葉」で意見を述べる準備ができます。また、多様な角度からの意見が集まることで、議論の質が高まります。提出は任意とし、プレッシャーにならないように配慮しましょう。
必要なものリストと環境づくり:集中できる「場」を用意する
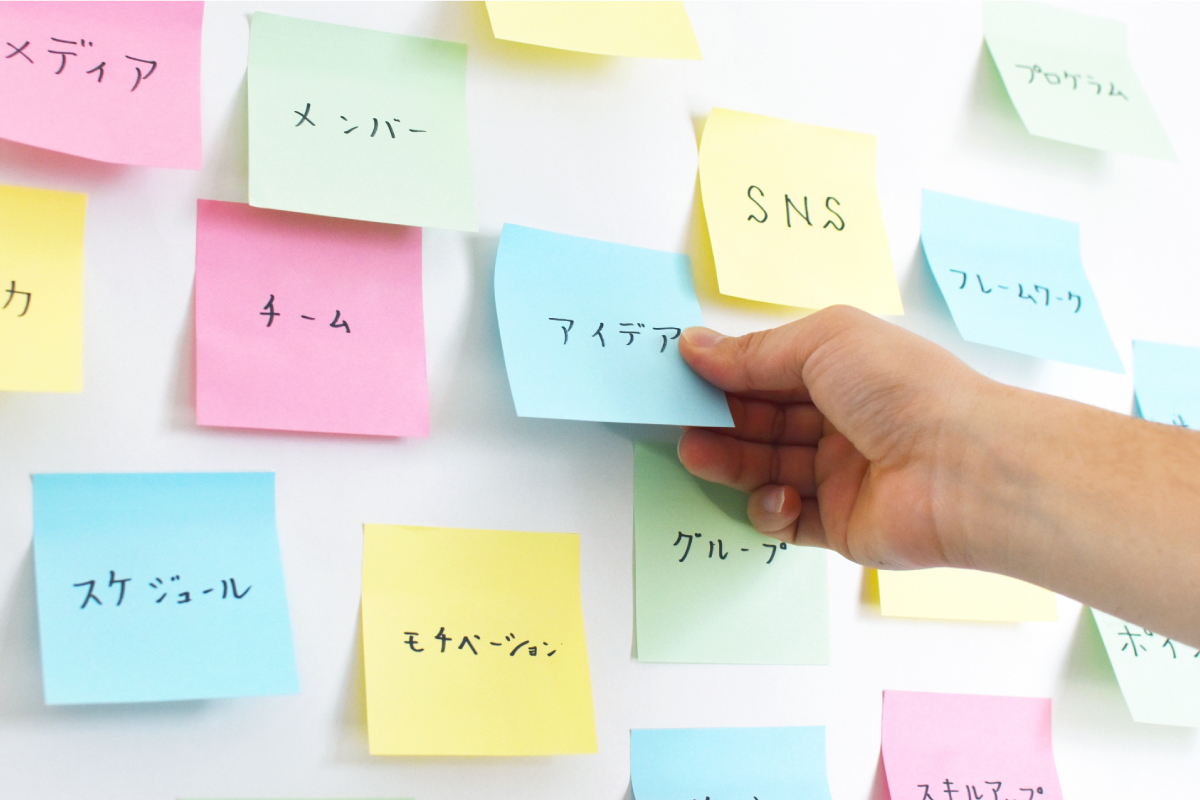
オフラインの場合
- 付箋(数色、多めに): アイデアを書き出し、グルーピングするのに必須です。
- 模造紙やホワイトボード: 全員が見えるように意見を貼り出したり、議論をまとめたりするのに使います。
- 太めのカラーペン(数色): 付箋や模造紙に書き込む際に見やすくするためです。
- プロジェクターやモニター(任意): 資料共有やオンラインツールの併用時に。
- 飲み物やお菓子: リラックスした雰囲気作りに役立ちます。
- その他: タイマー、カメラ(記録用)、ネームプレートなど
オンラインの場合
- ビデオ会議ツール(Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなど): 安定した接続環境と、ブレイクアウトルーム機能があると便利です。
- オンラインホワイトボードツール(Miro、Mural、Google Jamboardなど): 付箋機能、図形描画、投票機能などがあり、オフラインに近い感覚で共同作業ができます。無料プランやトライアルで事前に操作性を確認しておくと良いでしょう。IT企業である貴社(菊池さん)なら、これらのツールは比較的スムーズに導入できるかもしれませんね。
- 参加者へのお願い: 安定したインターネット環境、マイク・カメラの準備、静かな場所での参加などを事前にアナウンスします。
場の雰囲気づくり
- 明るく開放的な空間を選びましょう。
- 必要に応じて、心地よいBGMを小さな音で流すのも効果的です。
- ワークショップのテーマに合わせた装飾を少し施すだけでも、気分が高まります。
社長の心構え:「引き出す」ことに徹するファシリテーターへ
社長自らがワークショップに参加し、ファシリテーター(進行役)を務める場合、特に重要な心構えがあります。それは、「答えは社員の中にある」と信じ、社員の意見や想いを最大限に「引き出す」ことに徹することです。
- 指示や評価はNG: 「こうあるべきだ」「それは違う」といった社長の意見や評価は、社員の発言を萎縮させてしまいます。ワークショップの場では、社長も「一参加者」であるという意識を持ち、フラットな立場で議論に参加しましょう。(これは、権限委譲が少し苦手と感じている菊池さんにとって、新しいリーダーシップの形を発見する機会になるかもしれません。)
- 質問と傾聴が鍵: 「なぜそう思うの?」「具体的にはどういうこと?」「他にはどんな意見があるかな?」といった開かれた質問を投げかけ、社員が自由に、そして深く考えられるように促します。そして、どんな意見もまずは最後まで真摯に「聴く」姿勢が大切です。
- 議論の触媒となる: 社長自身の経験談や創業時の想いを、適切なタイミングで「一つの意見」として共有することは、議論を活性化させる良い触媒となり得ます。ただし、それが「社長の鶴の一声」にならないよう注意が必要です。
- 安心・安全な場を作るためのグランドルール: ワークショップの最初に、参加者全員で守るべきルール(グランドルール)を設定しましょう。
- 例:「役職や年齢に関係なく、自由に発言する
- 例:「他人の意見を批判したり、否定したりしない」
- 例:「結論を急がず、多様な意見を歓迎する」
- 例:「発言しない自由も認める(ただし、積極的に参加しようという気持ちは持つ)」
- アイスブレイクで緊張をほぐす: ワークショップの冒頭で、簡単な自己紹介や、仕事とは関係ないテーマでの短い雑談など、参加者の緊張をほぐし、話しやすい雰囲気を作るためのアイスブレイクを取り入れましょう。
「最近あった嬉しかったこと」「もし1週間休みが取れたら何をする?」など、ポジティブな話題が良いでしょう。
ワークショップ実践編:ステップ・バイ・ステップで社員の“本音”と“お宝”を引き出す
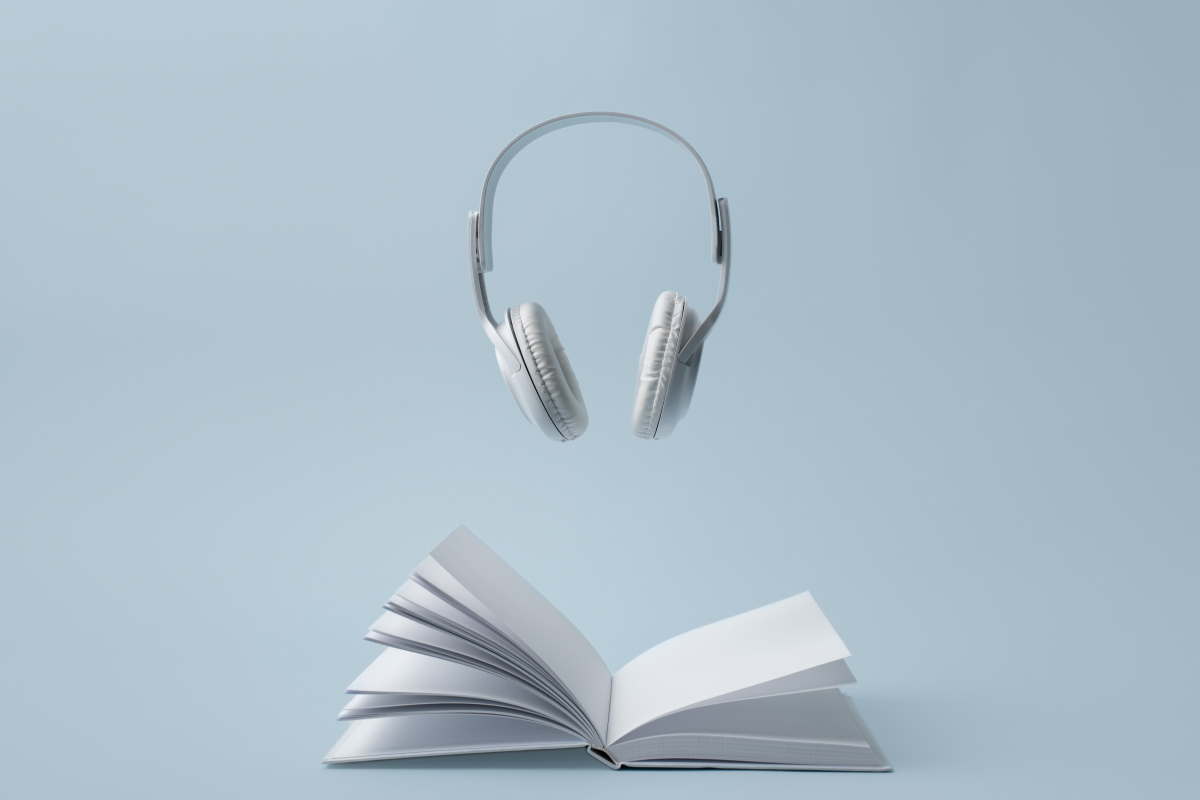
さあ、いよいよワークショップの実践です。ここでは、5つのステップで進める具体的な方法と、各ステップでの問いかけ例、ファシリテーションのコツをご紹介します。
各ステップで出てきた意見やキーワードは、付箋に書き出し、模造紙やオンラインホワイトボードに貼り出して「見える化」していくのがポイントです。
Step 1:「私たちの顧客は誰? その顧客は何に最も困り、何を心から喜ぶ?」
- 目的: 顧客への理解を深め、顧客視点を全員で共有する。
- 問いかけ例:
- 「私たちが最もお役に立てているお客様は、具体的にどんな方々でしょうか?(業種、規模、担当者の役職、抱えている課題など、ペルソナを具体的にイメージしてみましょう)」
- 「そのお客様が、私たちの商品やサービスに出会う前、一番困っていたこと、悩んでいたことは何だったでしょうか?」
- 「お客様は、どんな時に私たちに『ありがとう』『本当に助かった』と言ってくださいますか? その時の具体的な言葉や表情を思い出してみましょう。」
- 「逆に、お客様からお叱りを受けたり、ご不満をいただいたりした経験はありますか? それは何が原因だったでしょうか?」
- 進め方のコツ:
- まずは個人で考え、付箋に書き出し、その後グループで共有し、議論を深めます。
- 参加者それぞれが持つ「具体的な顧客像」や「実際のエピソード(成功談・失敗談)」を出し合うことで、血の通った顧客理解が進みます。
- 可能であれば、事前に顧客アンケートを実施したり、代表的なお客様数名にヒアリングしたりした結果を共有するのも効果的です。
Step 2:「私たちは顧客にどんな“お役立ち”(提供価値)を提供できている?」
- 目的: 自社が顧客に提供できている具体的な価値を洗い出し、成功体験を共有することで、社員の自信と誇りを醸成する。
- 問いかけ例:
- 「Step 1で出てきたお客様の悩みや課題に対し、私たちは具体的にどんな商品・サービス・サポートを提供し、どのように解決のお手伝いができていますか?」
- 「その結果、お客様のビジネスや状況は、どのように良い方向へ変わりましたか?(例:売上が上がった、業務効率が改善した、新しいことに挑戦できたなど)」
- 「数ある選択肢の中から、お客様が私たちを選び続けてくれているのは、私たちのどんな点(商品、技術、対応、人柄など)を評価してくれているからでしょうか?」
- 進め方のコツ:
- 「〇〇社の△△様から、こんな風に感謝されたんです!」といった、ポジティブな体験談を積極的に引き出しましょう。具体的なエピソードは、自社の提供価値をリアルに描き出します。
- 単に「製品が良い」だけでなく、「問い合わせへの対応が早い」「親身に相談に乗ってくれる」といったプロセスや関係性における価値も重要な“お宝”です。
Step 3:「競合と比べて、ここが違う!『私たちならでは』の強み・魅力は何か?」
- 目的: 自社の独自性や、競合他社に対する差別化ポイントを明確にする。
- 問いかけ例:
- 「お客様は、私たちと似たようなサービスを提供している会社を他に知っているでしょうか? もし知っているとしたら、それらの会社と比べて、お客様はなぜ最終的に私たちを選んでくれたのだと思いますか?」
- 「『〇〇社さん(自社)にしかできない』『〇〇社さんだからお願いしたい』とお客様に言われる(あるいは、そう思われていると感じる)のは、どんな点でしょうか?」
- 「私たちが『当たり前だ』と思って日々行っていることの中に、実は他社にはない、あるいは真似できない特別な強みや魅力が隠れていませんか?」
- 進め方のコツ:
- 事前に主要な競合他社の情報を整理し、参加者で共有しておくと、比較がしやすくなります。(ただし、競合批判にならないように注意)
- 顧客アンケートやインタビューで「当社を選んだ理由」といった項目があれば、その客観的なデータを参考に議論するのも有効です。
- 「品質」「価格」「スピード」といった一般的な言葉だけでなく、「〇〇な状況における△△というきめ細やかな対応力」のように、具体的な言葉で表現することを目指しましょう。
Step 4:「私たちが日々の仕事で、無意識にでも大切にしている『価値観』『こだわり』『譲れない想い』は何か?」
- 目的: 企業文化や組織のDNA、社員の行動の源泉となっている目に見えない「価値観」を言語化する。
- 問いかけ例:
- 「創業時から(あるいは、入社してから今まで)変わらず、この会社が大切にし続けていること、守り続けていることは何でしょうか?(ここで菊池さんの創業時の想いやエピソードを語っていただくのも効果的です)」
- 「どんなに忙しくても、あるいは困難な状況でも、『これだけは譲れない』『こうありたい』と思う仕事の進め方やお客様への接し方はありますか?」
- 「もし自分たちがお客様の立場だったら、どんな会社を信頼し、心から応援したいと感じるでしょうか? そのために、私たちはどうあるべきだと思いますか?」
- 「この会社で働いていて、『うちの会社らしいな』と感じる瞬間はどんな時ですか?」
- 進め方のコツ:
- このステップは、抽象的な問いが多くなるため、具体的なエピソードから深掘りしていくのがポイントです。「なぜ、そのように行動したのですか?」「その行動の背景には、どんな想いがあったのですか?」と、行動の裏にある「想い」や「判断基準」を丁寧に引き出します。
- 「誠実さ」「挑戦」「チームワーク」「顧客第一」といったキーワードだけでなく、「〇〇な状況でも、△△を優先する」といった、具体的な行動レベルでの価値観を明らかにできると理想的です。
Step 5:「これまでの“お宝”を統合し、『私たちの約束(ブランドプロミス)』を言葉にすると?」
- 目的: ここまでで発掘された「顧客像」「提供価値」「強み」「価値観」といった“お宝”を統合し、ブランドの核となる約束(社会や顧客に対するコミットメント)を、参加者全員で共創する。
- 進め方のコツ:
- Step 1~4で出てきたキーワードや重要なフレーズが書かれた付箋を、模造紙やオンラインホワイトボードに見える形で整理し、関連性の高いもの同士をグルーピングします。
- グループ化された塊の中から、特に自社らしさを表し、顧客や社会にとって価値があり、かつ社員が共感できる、最も重要な言葉やコンセプトを選び出していきます。(投票形式なども有効)
- それらの言葉を組み合わせ、「私たちは、〇〇な(顧客像・社会)に対し、△△(独自の強み・らしさ)を活かして、□□(大切にする価値観・姿勢)を胸に、××(提供する究極の価値・約束)を実現します」のような型を参考にしながら、ブランドプロミスとして数行の短いフレーズやステートメントにまとめてみます。
- これは「正解」を出す作業ではありません。全員で意見を出し合い、議論を重ね、何度も言葉を磨き上げていくプロセスそのものが重要です。全員が「これこそが、私たちの約束だ!」と納得できる言葉を見つけ出すことを目指しましょう。
社長が輝く!ワークショップ・ファシリテーションの極意

社長自らがワークショップのファシリテーターを務めることは、社員の想いを直接感じ取り、共に未来を描く上で非常に有意義です。しかし、その役割を効果的に果たすためには、いくつかの「極意」があります。
- 「なぜ?」を重ねる質問力と、答えやすい雰囲気づくり:
社員の表面的な言葉だけでなく、その奥にある本音やアイデアを引き出すためには、「なぜそう思うのですか?」「もう少し具体的に教えていただけますか?」といった深掘りの質問が不可欠です。ただし、詰問調にならないよう、あくまでも「もっと知りたい」という好奇心と敬意を持って問いかけましょう。また、「どんな意見でも大丈夫ですよ」「間違っていても構いません」といった言葉かけで、心理的安全性の高い、答えやすい雰囲気を作ることが大切です。 - 最後まで「聴き切る」傾聴の姿勢:
社員が話し始めたら、途中で遮ったり、自分の意見を挟んだりせず、まずは最後までじっくりと耳を傾けましょう。「うんうん」「なるほど」と頷きながら聴くことで、話し手は安心して自分の想いを言葉にしやすくなります。 - 時間管理と進行のバランス感覚:
ワークショップは限られた時間で行われます。各ステップに適切な時間配分を行い、議論が白熱して長引いた場合でも、全体の進行を見ながら柔軟にコントロールするバランス感覚が必要です。時には、「素晴らしい意見がたくさん出ていますが、そろそろ次のステップに進みましょうか」と、優しく軌道修正することもファシリテーターの役割です。 - ネガティブな意見や反対意見への建設的な対処法:
ワークショップでは、現状への不満やネガティブな意見、あるいは他の人とは異なる反対意見が出てくることもあります。これらを頭ごなしに否定したり、無視したりしてはいけません。まずは「そう感じるのですね」「貴重なご意見ありがとうございます」と受け止め、その背景にある課題意識や改善へのヒントとして活かす視点を持ちましょう。「どうすれば、その点がもっと良くなると思いますか?」と、建設的な議論に繋げることが大切です。 - 多様な意見の尊重と、納得感のある集約:
声の大きな人の意見ばかりが通ったり、一部の参加者しか発言しなかったりする状況は避けなければなりません。全員が平等に発言できる機会を作り、異なる意見や視点を尊重する雰囲気を作ることが重要です。最終的に意見を集約する際には、多数決だけでなく、少数意見の中にも重要なヒントがないかを考慮し、全員がある程度納得できる形でまとめるプロセスを大切にしましょう。
まとめと次のステップ:発掘した“お宝”を、会社の成長エンジンに変えるために

素晴らしいワークショップが終わり、社員の皆さんと共にたくさんの“お宝”を発掘できたとします。しかし、それで終わりではありません。大切なのは、その“お宝”を、これからの会社の成長エンジンへと変えていくことです。
- ワークショップ成果のドキュメント化と全社共有:
ワークショップで決定した「ブランドプロミス」や、そこに至るまでの議論の過程、発掘された「強み」「大切にしている価値観」などを、誰にでも分かりやすいように資料にまとめ、ワークショップに参加しなかった社員も含め、全社員で共有しましょう。社内報やイントラネットへの掲載、社内勉強会の開催などを通じて、何度も繰り返し伝えることが重要です。 - 発掘した“お宝”の具体的な活用例(菊池さんの課題解決に向けて):
- 「見せ方」の刷新で、企業の魅力を再定義する:
- 発掘された「強み」や「価値観」、「ブランドプロミス」を基に、心に響くブランドストーリー、キャッチコピー、タグラインなどを作成します。
- それらを、ウェブサイト、会社案内、提案資料、名刺といったあらゆるコミュニケーションツールに一貫して反映させ、デザインコンセプトの基盤とします。(この「伝える」部分こそ、私たち株式会社DIANTが得意とする領域です。)
- 「採用力」の強化で、共感する仲間を集める:
- 求人広告や採用サイトで、給与や待遇だけでなく、自社が大切にしている価値観や、働くことのやりがい、社会への貢献といった「らしさ」を具体的に発信します。
- これにより、企業の理念に共感する人材が集まりやすくなり、入社後のミスマッチを防ぎ、社員の定着率向上にも繋がります。
- 「見せ方」の刷新で、企業の魅力を再定義する:
- 「社内エンゲージメント」の向上で、一体感のある組織を創る:
- 発掘された「価値観」や「ブランドプロミス」を、社員の行動指針や評価制度、日々のコミュニケーションの参考にします。
- 社員一人ひとりが「自分たちの会社は何を目指し、何を大切にしているのか」を常に意識することで、仕事への誇りやモチベーションが高まり、組織としての一体感が醸成されます。
- 「成長戦略」の明確化で、未来への羅針盤とする:
- 明確になった「自社ならではの強み」と「顧客への約束」を基に、今後の事業展開の方向性や、新規サービスの開発、ターゲット市場の選定など、より具体的で、かつ自社らしい成長戦略を定めることができます。
- 明確になった「自社ならではの強み」と「顧客への約束」を基に、今後の事業展開の方向性や、新規サービスの開発、ターゲット市場の選定など、より具体的で、かつ自社らしい成長戦略を定めることができます。
- 継続的な取り組みの重要性:
ブランドは、一度作ったら終わり、というものではありません。市場環境や顧客のニーズは常に変化します。
大切なのは、定期的に社員と共に自社の「お宝」を見つめ直し、時代に合わせて磨き上げていくという、継続的な取り組みです。
このワークショップが、貴社ならではの「共感型ブランド」の源泉を発見し、社員の皆様が一丸となって未来を切り拓く、その大切なきっかけとなることを心から願っています。
そして、発掘されたそのかけがえのない“お宝”を、顧客や社会に最も魅力的な形で伝え、確かな成果へと繋げていくためのデザイン戦略やクリエイティブ制作においても、私たち株式会社DIANTがお手伝いできることがたくさんあります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
ブランディングデザインにご興味がございましたら、ぜひ以下のリンクもご確認ください。